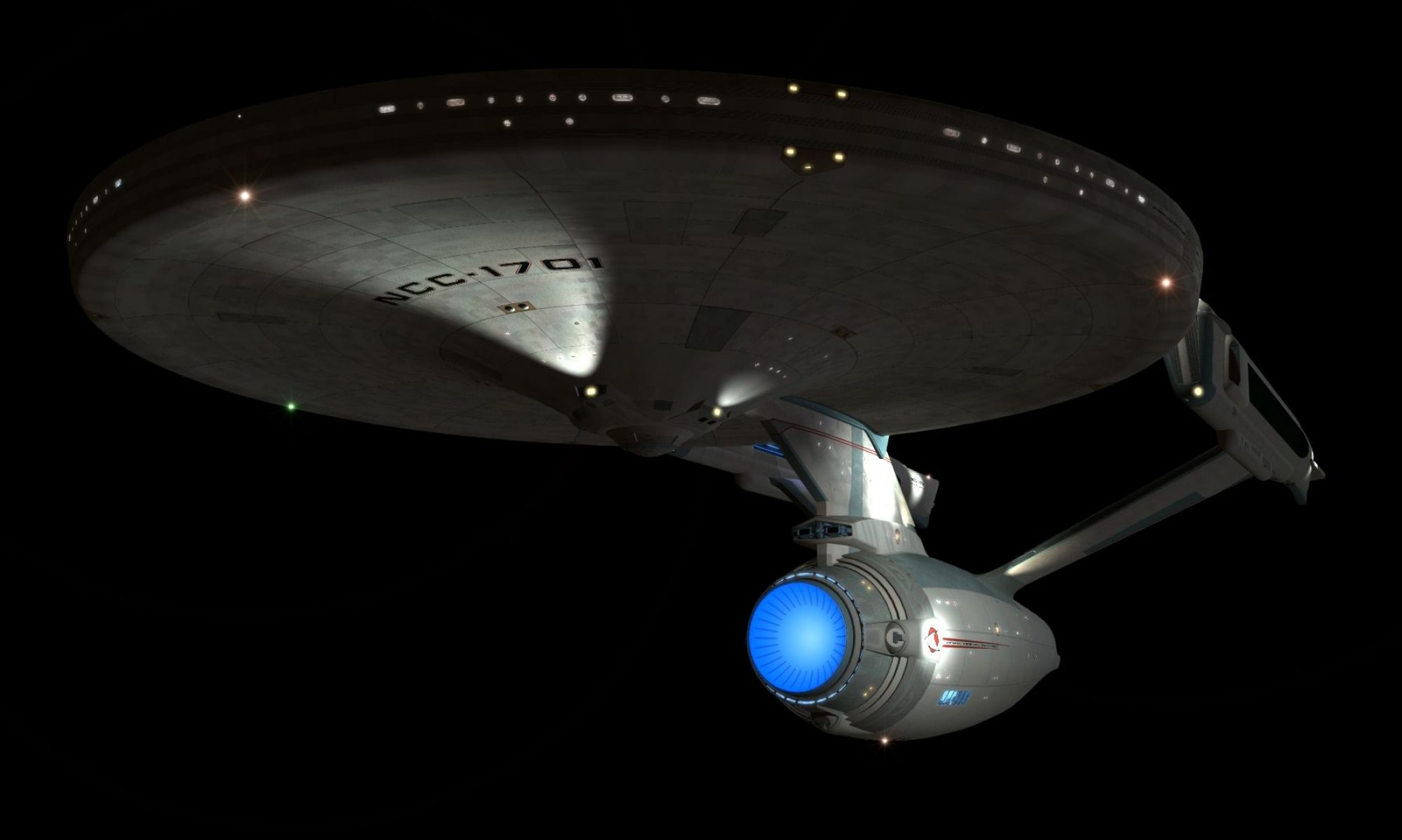勉強することが増えたとかいう前に、そもそもポンコツになりつつあるという話を吐露します。
昨日、桜の開花宣言後、初めての週末。意気揚々と長居公園のトレーニングジムへバスで向かい、公園内の周回コースを4周(約11キロ)回るランニングをスタート。
公園内は同じようなランナーはもちろん、広場で遊ぶ子供たち、桜の木の近くで弁当を広げる家族連れでにぎわっていた。
そして3周目を走っている途中でポンコツは気づく。プーマのランニングパンツが前後逆にはていることを。
慌ててコースから外れるポンコツ。上着のTシャツ、ウインドブレーカーを思いっきり下に伸ばしてパンツの太もも部分に記されているプーマのロゴを隠そうとするも願いかなわず。
。。後ろ向きのプーマ。。
見る人が見たらわかるだろう。。。ランニングを途中で切り上げ、人目を避けるようにジムに戻り着替える。爽快感とは真逆の後味の悪さを残して長居公園を後にした。
実はジムについた時、ズボンのチャックが全開だったことに気が付く。移動時間20分の9割はバスの中で座っていたので「ま、いいか」と思っていた矢先に、ランパンを前後逆にはいて周回コースを周回するという痴態をおかす自分にトホホなのだよ。
勉強しなきゃとか前に、そもそもの脳みそがポンコツになっている、むしろコッチの方が何とかしないとまずい、というお話でした。