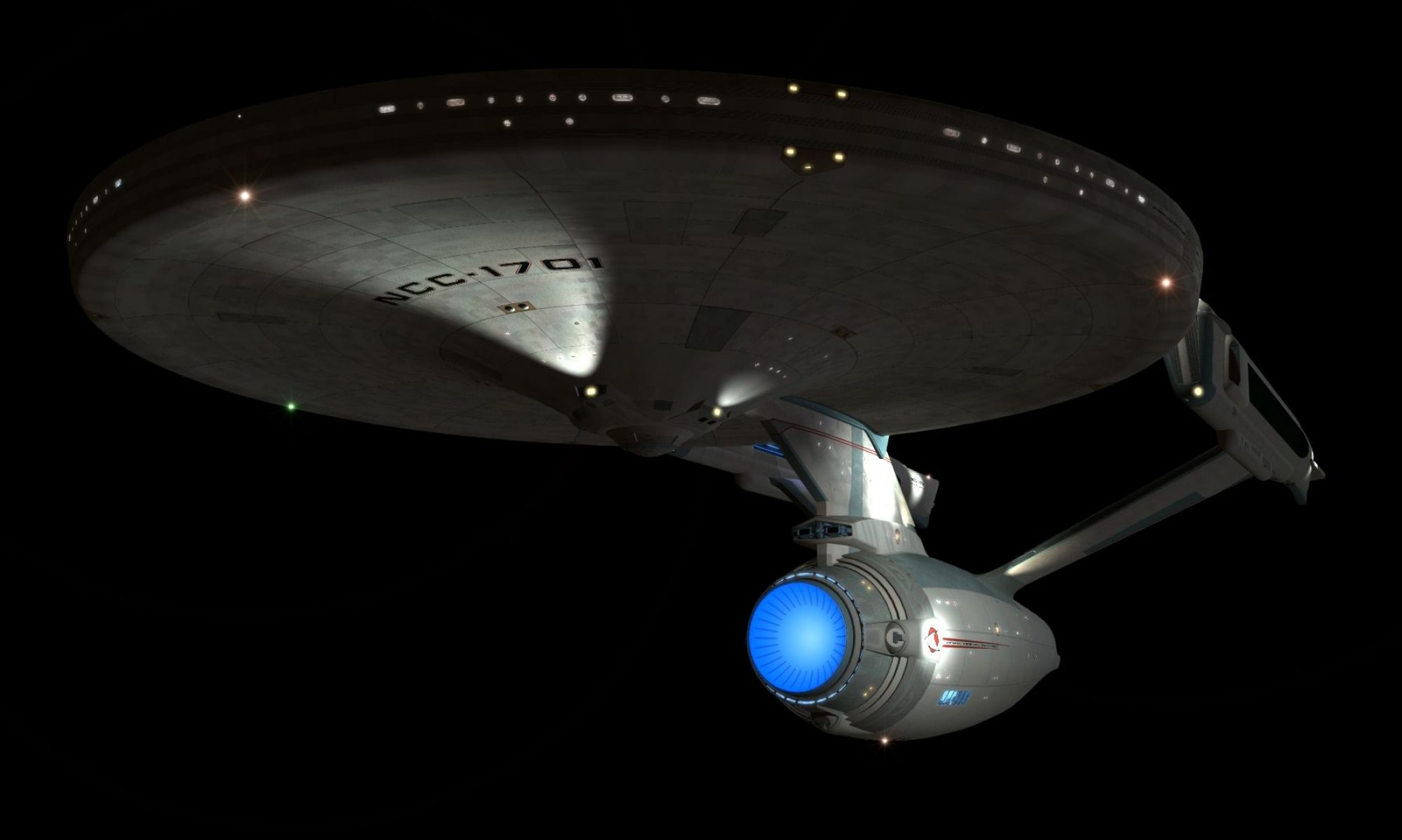この前、仕事で電話したら相手に「ガチャ切り」されたお話です。
ただいま仕事でとあるアンケートの事務局の役割をしておりまして、メールで送られてくるエクセルの回答ファイルをチェックしていた私。
とある回答ファイルに手が止まる。
その内容は、最初の一問のみに回答し、残り99%が未記入というもの。
事務局のリアクションとしては、当然、「ファイルの内容がほとんど未記入となっておりますが、回答ファイルにお間違いはありませんか?ご確認いただければ幸いです」となる。メールを送る。
その後、相手から帰ってきたメールをみると。。
「特に変わりありません」とある。
???? こりゃ 電話するしかないな・・・
電話する。
「事務局のデュアルと申します。Aさん、いらっしゃいますか?」
で、Aさんに取り次いでもらったと思ったら、そのAさん、いきなり無言。
「Aさんですか?」と確認したら、「・・・はい・・」とふてくされモード
意味が解らないまま、アンケートの回答について確認すると、これまた要領を得ない。「あの回答はあれでよい」とか、「(記入済みのものは)別に送った」とか・・・
こちらはあくまでお願いする立場。なので 平身低頭、上から目線(笑)で応対し、「たいへんお手数ですが ”別に送った” 回答ファイルを再送していただけないでしょうか?」と言ったところ
「あ~、もう忙しいから、もういいです!(ガチャ!)」
といった顛末だった。
アンケートというのは、100社以上にご協力をいただいている「環境」に関するもの。電気・ガスのエネルギーの利用状況とかね。
毎年やっているけど、回答率は95~100% 皆さん よくご協力をいただいているアンケートなのだ。
ちなみに、このAさん、数年前からアンケートに協力をしてくれていた。
電話でも話したことがある。
しかし、昨年は”業務が忙しいので回答できない”と電話で連絡があった。
で、今年の反応、というか、電話での態度。
他人事ながら心配になった。 Aさん、かなり疲弊しているんじゃないかと。。
そういえば、電話を取り次いてくれた人も、「Aさんいらっしゃいますか?」と聞いたら緊張感が増したような気がした。そして、職場の電話でガチャ切り・・・大丈夫か?と
自分のことを振り返ってみて、最初の会社で月200時間以上の残業をしていた時期は、とにかく怒っていた。なんか、その怒りのエネルギーで働いていたフシもある。
一方、仕事の関係者でもとにかく短気、沸点が12℃くらいかと思うほど、怒ってばかりの上司や客先もいたのは確かだ。
でもね。。。ここ10年の働き方改革とやらで、そんなピリピリモードなんて忘れていたし、まさか社外との電話で、その一端を垣間見るとは思わなかった。
と言いつつも、思い返せば返すほどAさんの情緒が心配だ。
フツーとは思えない。
サラリーマンが情緒不安定になったら真っ先に休養を取らねばならないと思ってる私。Aさんに「休んだ方がいいですよ」というメールを打とうとして、寸でのところで思いとどまった、とさw